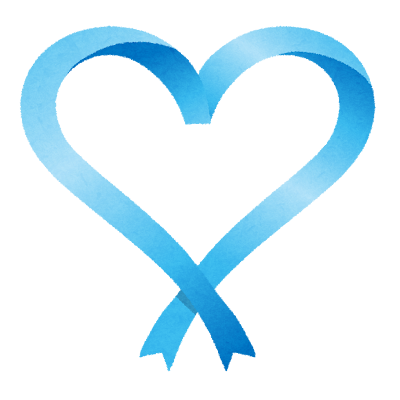朝5時、目覚ましが鳴る前に目が覚めた。部屋はまだ暗い。昨日もほとんど眠れなかったけれど、起きなければならない。母が待っている。リビングへ向かうと、薄暗い中で静かに母が寝息を立てているのが見えた。その姿を見ながら、私は小さく息をつく。今日も一日が始まる。
キッチンに立ち、お湯を沸かしながら冷蔵庫を開ける。昨日作っておいたお粥を取り出して鍋で温め始める。このお粥も、母がどこまで食べてくれるかわからない。でも、何もしないわけにはいかない。母のために食事を作るのは、私にできる数少ない「母らしさ」を守る手段だからだ。
母は5年前、認知症と診断された。それまで元気で独り暮らしもしていた母が、ある日「スーパーの場所が分からなくなった」と言ったとき、私はただの物忘れだと思った。でも、そのうち同じ話を何度も繰り返し、時には財布をどこに置いたかもわからなくなることが増えた。病院に行ったとき、医師から告げられた「認知症」という言葉に、頭が真っ白になったのを今でも覚えている。
当時、私は都内のIT企業で働いていた。プロジェクトマネージャーとして忙しい毎日だったけれど、仕事はやりがいもあり、充実していた。でも、母が介護を必要とするようになると、仕事と家庭の両立という現実に直面した。最初は何とかなるだろうと思っていたけれど、甘かった。
朝の準備を終えると、母を起こす時間だ。リビングの椅子で寝てしまった母に声をかける。「お母さん、朝だよ。ご飯食べよう。」少し戸惑った表情で私を見る母。今日の母は私の顔を覚えているだろうか。最近では、私のことを「誰?」と聞くことも増えてきた。
母を椅子から立たせ、ゆっくりと歩かせてダイニングテーブルに連れていく。その途中で「どこに行くの?」と母が聞く。「朝ごはんだよ」と言っても、母はまたすぐに「どこに行くの?」と繰り返す。こういうとき、心がズキズキと痛む。怒るわけにはいかないとわかっていても、何度も同じやり取りを繰り返すうちに、私の中でイライラが募っていくのがわかる。
母の食事を終えさせるのにも一苦労だ。箸をうまく持てなくなった母が、「私はもう食べた」と言い張ることもある。それでも、少しずつスプーンを口元に運び、食べさせる。これが私の毎朝の日課だ。
母をデイサービスに送り出した後、私は急いで出勤の準備を始める。会社に向かう途中、スマートフォンでスケジュールを確認し、今日のタスクを頭の中で整理する。仕事のスイッチを入れるのは簡単ではない。母のことが常に頭の片隅にあるからだ。
職場に着くと、部下たちの報告を聞きながら、メールをチェックする。上司からのプレッシャーや納期の調整に追われる日々だが、仕事は私にとって唯一「自分らしさ」を取り戻せる場所でもある。ここだけは「介護者」ではなく、「自分」でいられる。だからこそ、仕事を辞めるという選択肢はなかなか選べなかった。
昼休み、ふとスマホが鳴る。デイサービスからの着信だ。「お母さまが少し不安定な様子で……」という連絡に、胸が締めつけられる。すぐに仕事に戻らなければならないが、母のことが気がかりで集中できない。こうしたことが重なると、「仕事を辞めたほうがいいのだろうか」と悩む自分がいる。
夜、家に帰ると、母はソファに座ってテレビを見ていた。私を見ると「あら、おかえり」と言う。その瞬間だけ、母が以前の母に戻ったような気がする。だが、次の瞬間には「あなた誰?」と尋ねられる。私の心は少しずつ蝕まれていくようだ。
そんな日々の中で、唯一救いだったのは、地域の介護支援センターのケアマネージャーと話したことだった。デイサービスやショートステイの提案を受け、少しずつ介護の負担が軽減された。また、介護者同士が集まる会に参加することで、自分だけが苦しんでいるのではないと知ることができた。それでも、心の中に「自分は十分にやれているのだろうか」という罪悪感は消えない。
私は今日も母を支えながら、自分の生活を何とか保っている。介護と仕事の両立は簡単ではない。それでも、母の何気ない笑顔や一言が、私にとっての支えになっているのは確かだ。この生活がいつまで続くかわからないけれど、私はまた明日も「お母さん、おはよう」と声をかけるつもりだ。それが、今の私にできる精一杯だからだ。また、「お母さん、おはよう」と声をかけるのだろう。