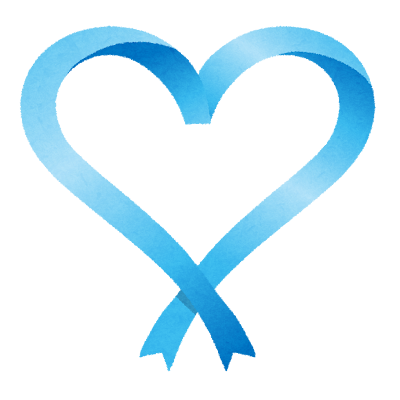いつもの祖母が少し違う日
静かに訪れた変化
「おばあちゃん、今日は何してたの?」
私がそう聞くと、祖母は少し困ったような顔をして「んー、何してたっけ?」と首をかしげた。いつもなら庭の草花の手入れや、手芸に没頭していた祖母が、そんな曖昧な返事をするのは珍しかった。けれど、その瞬間は深く気にすることもなく、「年を取ると少し忘れっぽくなるのは仕方ないよね」と思っただけだった。
祖母は家族の中心にいる人だった。幼い頃から、私は祖母に抱かれて育った。学校での出来事を聞いてくれる人、夜に絵本を読んでくれる人、熱を出したときに一晩中看病してくれる人――それが私の祖母だった。私にとって、祖母はいつでも「安心感」を象徴する存在だった。
しかし、そんな祖母が少しずつ変わり始めたのは、70代後半を迎えた頃のことだった。最初の変化は小さく、ほとんど気づかないほどだった。
初めての違和感
異変に気づいたのは、祖母が夕食の準備をする際のことだった。料理好きで手際の良い祖母は、家族のために和食を中心とした美味しい料理を毎日作ってくれていた。しかしその日、台所に立つ祖母の背中に、普段の余裕がないように感じた。何度も冷蔵庫を開けては閉め、鍋の中を覗き込みながら、どこか落ち着かない様子だった。
「何か手伝おうか?」と声をかけると、祖母は少し焦ったように「いいの、いいの。でも……何を作ろうとしてたんだっけ?」と答えた。その言葉を聞いた瞬間、私は少し驚いた。いつもなら頭の中にしっかりと献立があって、それをスムーズに進めていく祖母が、「忘れる」ことに戸惑っているようだったからだ。
この出来事を母に話すと、「年を取るとそういうこともあるわよ」と笑われた。確かにそうかもしれない――そう自分に言い聞かせたが、それからしばらくの間、祖母の行動を少し気にするようになった。
増えていく「忘れる」瞬間
その後も、祖母が「忘れる」瞬間は増えていった。たとえば、孫の私たちに「おはよう」と言った数分後に、「あら、もう起きてたの?」と再び挨拶をしてきたり、買い物リストを書いたのにそれを家に置いてきてしまったり。それ自体は小さな出来事だったが、頻度が高まるにつれて、「普通の物忘れ」とは少し違うのではないかという疑念が頭をよぎり始めた。
最も印象的だったのは、祖母が「家の電話番号」を忘れてしまったときだった。長年暮らしてきた家の番号をすらすら言えなくなり、代わりに他人事のような笑顔で「最近、電話ってあまり使わないからね」と言ったのだ。その笑顔には何か隠そうとしているような気配があった。
「これって、ただの老化なのかな?」
私の疑問を母に伝えたが、母も「まだ様子を見よう」と言うだけで、それ以上の行動を起こそうとしなかった。家族全員がどこかで「そんなわけない」と自分たちを納得させようとしていたのだと思う。
決定的な出来事
転機が訪れたのは、祖母が買い物に出かけた日だった。いつもは1時間ほどで戻ってくるのに、その日は3時間経っても帰ってこない。心配になった母と私は、近所を探し回った。スーパーに寄る予定だったのでそこに向かったが、店内にも駐車場にも祖母の姿はなかった。
その後、私たちは祖母を家から2キロほど離れた公園で見つけた。祖母はベンチに座り、ハンドバッグを膝に置いて、何か考え込むようにぼんやりしていた。
「おばあちゃん、ここで何してたの?」と声をかけると、祖母は少しほっとした表情で「道が分からなくなっちゃって……でも、誰かが迎えに来てくれると思って待ってたの」と答えた。
この出来事は、私たち家族に大きな衝撃を与えた。「道に迷う」というのは、それまでの祖母からは考えられないことだったからだ。その日の夜、私たちは初めて「もしかして認知症かもしれない」という言葉を口にした。
病院への一歩
その後、母が地域のかかりつけ医に相談し、専門の認知症外来を予約した。診察の日、祖母は少し緊張した様子だったが、それでも診察室では穏やかに振る舞っていた。医師からいくつかの質問を受けた祖母が、「今日は何年の何月ですか?」という問いに答えられなかったとき、私たちは改めて事態の深刻さを実感した。
MRI検査や詳細な質問紙による診断の結果、祖母は「アルツハイマー型認知症の初期段階」と診断された。医師は丁寧に説明してくれたものの、その言葉の重みは家族全員に大きなショックを与えた。特に祖母は、自分が「認知症」と診断されたことに少なからずショックを受けているようだったが、それでも「みんなに迷惑かけないように頑張るからね」と笑顔を見せた。
その笑顔を見たとき、私は胸が締め付けられるような思いだった。「迷惑」という言葉を祖母が口にすること自体、私にとっては受け入れがたいものだった。私たちは「大丈夫だよ」と励ますしかできなかったが、祖母の笑顔の裏にある不安や恐れが伝わってきて、言葉を失った。
新たな日常の始まり
診断を受けた翌日から、私たち家族の生活は少しずつ変わり始めた。まずは、祖母の日々の行動をサポートするための工夫が求められた。冷蔵庫や戸棚には、祖母が使うものを分かりやすく整理し、メモを貼るようになった。また、散歩や買い物には必ず家族の誰かが付き添うようにした。
祖母は時折「私はまだ元気よ」と笑って言うものの、日常の中で小さな困難が少しずつ増えていることを、家族全員が感じていた。物忘れや混乱だけでなく、感情の起伏も少しずつ目立つようになり、私たちも対応に苦労する場面が増えていった。
それでも、祖母が笑顔を見せる瞬間や、昔の話をしてくれる時間は、私たちにとって大切なひとときだった。「認知症になっても祖母は祖母だ」という思いを胸に、私たちは新しい日常に向き合う覚悟を決めたのだった。
祖母の認知症の物語はここから本格的に始まった。この時点で、私たちはまだ介護の大変さや未来の困難を具体的に想像することはできなかった。しかし、この診断の日をきっかけに、私たち家族の絆がさらに深まる物語が紡がれていくことになる。