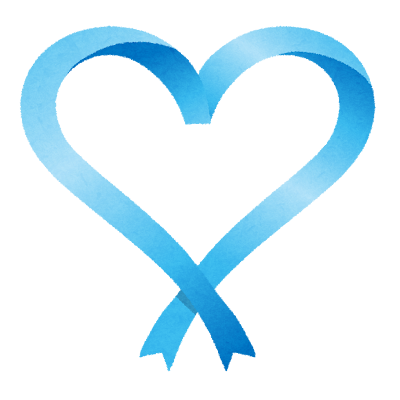介護が始まった日 ~人生の急転と新たな役割~
私の生活は、ある日を境に一変しました。それは、母が脳梗塞で倒れた日です。あの日の朝、母はいつも通り台所で朝食を用意してくれていました。キッチンから漂う味噌汁の香り、包丁で野菜を刻む音。そのすべてが、私にとって「いつもの風景」で、何の違和感もない平穏そのものでした。しかし、その平穏は突然の電話で打ち砕かれることになります。
「お母さんが倒れた」
電話口の向こうで父が震えた声でそう告げたとき、私はすぐに何か重大なことが起こったと悟りました。急いで病院に駆けつけると、そこには顔色の悪い母がストレッチャーで運ばれる姿がありました。医師から告げられたのは「脳梗塞」という言葉。治療が間に合ったおかげで命は助かったものの、右半身に麻痺が残り、日常生活に支障をきたすことが明らかでした。
退院後の選択肢
母が退院するまでの数週間、家族で何度も話し合いを重ねました。リハビリを続けながら生活するためにはどうすればいいのか?施設に入る選択肢もありましたが、母自身が「家で生活したい」と強く希望したため、在宅介護を選ぶことになりました。私はその時点ではっきりと決心しました。「母のために私ができることはすべてやろう」と。
しかし、その決心がどれほど大変な現実を意味するのか、当時の私はまだ十分に理解していなかったのです。
介護の準備
在宅介護を選択したものの、その準備は想像以上に大変でした。まず、家の環境を大きく変える必要がありました。母が安全に生活できるように廊下や階段に手すりを設置し、トイレをバリアフリー仕様に改装。ベッドも介護用の電動ベッドに買い替えました。一つ一つの準備には時間もお金もかかり、「これで本当に大丈夫なのか」と不安が尽きませんでした。
さらに、介護保険サービスの利用方法についても一から学ぶ必要がありました。地域包括支援センターのケアマネジャーに相談し、訪問看護やデイサービス、リハビリを組み合わせたケアプランを作成しました。書類の提出や手続きが複雑で、日中は仕事をしながら夜遅くまで調べ物をする日々が続きました。この時点で、介護は始まる前からすでに「生活を大きく支配するもの」だと感じていました。
最初の試練:退院後の生活
母が退院したその日、私たち家族にとって新たな日常が始まりました。最初に直面したのは、母がベッドから一人で起き上がれないという現実です。それまで当たり前だった「自分で動ける」ということが、いかに大きな自由であったかを痛感しました。母を抱きかかえて車椅子に移動させる作業は予想以上に体力を消耗し、初日は私も父も全身が痛くなるほどでした。
さらに、食事の時間も大きな課題でした。母は右手が使えないため、スプーンを使った食事にも介助が必要です。最初のうちは私もぎこちなく、母も遠慮がちでした。「ごめんね」と何度も口にする母に、「そんなこと言わないで」と笑顔で返しながらも、内心では「これがいつまで続くのだろう」と不安に押しつぶされそうでした。
感情の揺れと自己否定
介護が始まったばかりの頃、私は自分の感情を持て余していました。母の介護をする中で、「どうしてこんなことに」と現実を受け入れられない気持ちと、「自分がしっかりしなくては」という責任感が入り混じり、心が休まる瞬間がありませんでした。
母が夜中に何度もトイレに行きたがるたび、私も起きて手助けをしました。しかし、何度も繰り返される夜間の介助に疲れ果て、「少しくらい我慢してくれないかな」と思ってしまう自分がいました。その思いが浮かんだ瞬間、自分がひどい人間のように感じられ、涙が止まらなくなることもありました。
さらに、介護が原因で家族内の会話もぎこちなくなり、次第にストレスがたまりました。父や兄弟と意見が合わず、「私一人に負担が集中している」と感じる場面もありました。しかし、「母のためだから」という思いで自分を納得させるしかありませんでした。
小さな希望の光
そんな混乱の日々の中でも、母が少しずつ回復していく姿が、私にとっては唯一の希望でした。退院して1か月ほど経った頃、母が訪問リハビリの先生とともにリハビリを始めました。最初は手足を少し動かすだけで精一杯でしたが、ある日母が「今日は自分でスプーンを持てたよ」と嬉しそうに言った瞬間、私の心にも少しだけ光が差し込みました。
また、母がデイサービスから帰ってきたときに「今日はみんなとおしゃべりして楽しかったよ」と話してくれる姿を見て、介護の負担が少し軽く感じられるようになりました。小さな進歩や笑顔が、私自身を支える力になっていたのだと思います。