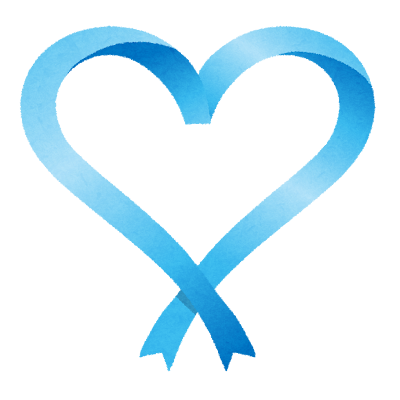第二部:最期の瞬間と家族の絆
訪問看護が始まってから数カ月が経ち、季節が秋から冬に移り変わる頃、彼の病状は徐々に悪化していきました。呼吸が浅くなり、痛みを訴えることが増え、会話も短く途切れるようになりました。それでも彼は、ご家族の前では気丈に振る舞い続けていました。「家族に心配をかけたくない」という思いが、彼の原動力だったのかもしれません。
ある日、奥さんから「主人の意識が朦朧としているようなんです」と連絡を受けました。急いで彼の家に向かうと、彼はベッドで目を閉じて静かに息をしていました。呼吸は不規則で、時折苦しそうな表情を浮かべていました。医師とも相談し、痛みを軽減するためのモルヒネを投与することになりました。
その夜、彼の家族全員が集まりました。奥さん、娘さんたち、そして孫たちもリビングに集まり、彼のベッドの周りで過ごしていました。普段は忙しくてなかなか集まれない家族が一堂に会する姿を見て、私は胸が熱くなりました。彼の奥さんは「主人が家族みんなと一緒に過ごせる時間を望んでいたから」と言いました。その言葉に、彼の家族への愛情の深さを改めて感じました。
夜が更ける中、彼の呼吸は徐々に弱くなり、意識も戻ることはありませんでした。しかし、不思議と部屋の中には悲壮感ではなく、温かい空気が流れていました。ご家族が手を取り合い、お互いに支え合いながら、彼の最期の時間を見守っていたからです。奥さんは彼の手を握りながら、静かに涙を流していました。
その瞬間が訪れたのは、夜明け前でした。彼の呼吸が止まり、静かに旅立ったのです。ご家族全員が彼の周りに集まり、それぞれの思いを胸に黙祷を捧げました。奥さんは「ありがとう。お疲れ様でした」と優しく声をかけ、娘さんたちも涙を浮かべながらその言葉に頷いていました。
私はその場に立ち会いながら、彼の人生の最後を支えられたことに感謝の気持ちを抱きました。同時に、自分の無力さを痛感する瞬間でもありました。「もっと何かできたのではないか」という思いが頭をよぎりましたが、ご家族の表情からは感謝と安堵の色が感じられ、それが私の心を少しだけ救ってくれました。
葬儀が終わった後、ご家族から手紙をいただきました。その手紙には「看護師さんのおかげで、主人の希望を叶えることができました。本当に感謝しています」という言葉が書かれていました。私はその手紙を読みながら、涙が止まりませんでした。この仕事の意義を改めて実感した瞬間でした。