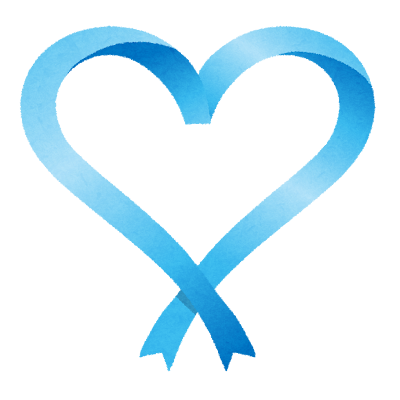突然の変化
私の名前は山田一郎、75歳。妻の陽子は72歳です。二人でつつましく暮らしながら、穏やかな老後を送ることを夢見ていました。しかし、その平穏な日々が突然終わりを迎えたのは、陽子が70歳になったばかりのある夏の日でした。
その日、私は庭の草むしりをしていました。朝から蒸し暑く、ふと「陽子も体調を崩していないか」と思いながら、手を止めて家の中へ戻りました。台所に入ると、陽子が床に倒れていました。彼女は顔を歪め、右側の手足が動かない状態で、微かに「あ……」と声を出していました。私は驚きと恐怖で体が震え、すぐに救急車を呼びました。
病院に搬送された陽子は、検査の結果、脳梗塞と診断されました。医師からは「軽度の発作ではありますが、右半身に麻痺が残る可能性が高いです」と告げられました。その言葉を聞いた瞬間、頭が真っ白になり、陽子のこれからの生活、そして自分たちの暮らしがどうなるのか、不安でいっぱいになりました。
陽子の入院中、私は毎日病院に通いました。彼女はリハビリに励んでいましたが、右手は思うように動かず、歩行も杖が必要な状態が続いていました。退院する日が近づくにつれ、私は自分が彼女を支えなければならないという責任感と、それに伴う不安で夜も眠れない日々が続きました。
初めての介護
退院後、私たちの生活は一変しました。これまで家事全般を担当していた陽子が、料理や掃除どころか、身の回りのことも満足にできなくなったからです。私は彼女を支えながら、全ての家事を引き受けることになりました。
まずは料理から始めました。陽子がよく作ってくれていた煮物や味噌汁を思い出しながら、インターネットでレシピを検索して試行錯誤しました。しかし、いざ作ってみると、味付けが安定せず、陽子は無理して食べているようでした。その姿を見て胸が痛みましたが、「頑張らなければ」と自分を奮い立たせました。
掃除や洗濯も、陽子の指導を受けながら行いましたが、慣れない作業に時間がかかり、毎日クタクタになりました。それに加えて、陽子のリハビリの付き添いや、薬の管理も行わなければなりませんでした。1日の予定がびっしり詰まり、私自身の自由な時間はほとんどなくなりました。
最初のうちは「なんとかなる」と思っていましたが、次第に現実の厳しさを思い知らされました。陽子の「できないこと」を目の当たりにするたびに、彼女自身も落ち込んでいるのが分かりました。そんな陽子を励ますべき立場の私が、逆に気持ちが沈んでいくこともありました。
心と体の限界
介護を始めて半年が経った頃、私の体に異変が現れ始めました。まず感じたのは慢性的な腰痛でした。掃除や陽子を支える動作が負担になり、朝起きるたびに腰が重く、曲がった状態でしか動けなくなることもありました。それでも、陽子の世話をする手を止めるわけにはいかず、痛みに耐えながら動き続けました。
夜、ようやく布団に入ると、疲れ果ててすぐに眠りにつくはずでしたが、逆に眠れない日々が続きました。「これがいつまで続くのだろう」と考え込んでしまい、朝になるとますます疲れが溜まるという悪循環に陥っていました。
孤独感も私を苦しめました。友人と会う機会はめっきり減り、陽子と家の中で過ごす時間がほとんどでした。子どもたちに助けを求めることも考えましたが、それぞれ仕事や家庭で忙しくしている様子を見て、「これ以上負担をかけてはいけない」と思い、連絡を控えていました。
そんな中、陽子がぽつりと漏らした一言が、私の心を深く揺さぶりました。「こんな風になってしまって、ごめんね」。その言葉に私は、何も言い返せませんでした。ただ陽子の肩を抱きしめ、「そんなこと言わないで」と声を絞り出すのが精一杯でした。