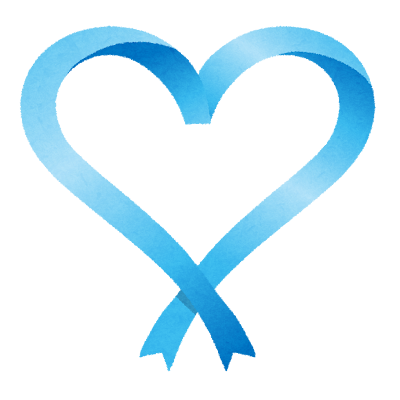変化は静かに訪れる
母はいつも穏やかで、手際の良い女性だった。どこにいても何をしていても、周囲に気を配り、私たち家族を見守る存在だった。料理が得意で、家に帰ると台所から漂ってくる香りが、どれだけ私たちの心を和ませてくれていたか分からない。
しかし、あるときから母に微かな変化が現れ始めた。その変化はあまりにさりげなく、私たち家族が気づくには少し時間がかかった。
「最近、トイレが近いのよ。」
母がそう言ったのは、ある静かな午後のことだった。私はその言葉を軽く聞き流し、「年のせいかもね」と答えただけだった。母も気にする素振りを見せなかったし、その程度の話だと思ったのだ。
だが、それからしばらくして、母は外出を控えるようになった。以前は友人と出かけたり、近所を散歩するのが日課だったのに、「外に出るのが面倒くさい」と言うようになった。私たちはその言葉の裏に隠された理由を、まだ理解していなかった。
初めての「助けて」
変化が明確になったのは、ある休日の出来事だった。家族みんなで外食に出かける途中、母が突然「あ、トイレに行きたい」と言い出した。慌てて近くのコンビニに駆け込んだ母は、トイレから出てくると、申し訳なさそうに「ごめんね、急に」とつぶやいた。
その時の母の表情は、私の心に残った。自分が何か迷惑をかけてしまったという負い目と、どうしていいか分からない戸惑いが混ざり合ったような、そんな顔だった。いつも家族の支えであろうとしていた母が、「助けて」と言っているように見えた。
私は軽く笑って「全然大丈夫だよ」と返したが、その後も母は何度かトイレに行くことを口にした。そして家に帰った途端、母はほっとしたような顔をして「やっぱり家が一番ね」と言った。
家族の反応
私がその日の出来事を父と兄に話すと、二人は意外にも深く気に留めなかった。父は「年を取るとそうなるもんだよ」と言い、兄も「誰だってトイレは近くなる」と軽く流した。
しかし、私は母の表情が気になって仕方がなかった。あの日、母の「ごめんね」という言葉がどれほどの勇気を必要としたのか、その重みを感じていたからだ。
私は夜中にインターネットで「高齢者 トイレが近い」「頻尿 原因」と検索を繰り返した。そこには、膀胱の機能低下や筋力の衰え、さらにはストレスや生活習慣が原因になる可能性が記されていた。
「もしかして病院に行ったほうがいいのかな。」
翌朝、私は母に軽くそう提案した。しかし母は首を横に振り、「こんなことで病院に行くなんて、恥ずかしい」と言った。
その言葉を聞いたとき、私は初めて「排泄」に関する話題が、どれほどデリケートなものかを知った。自分の体に起きている変化を受け入れることの難しさ。そして、それを家族に打ち明けることの勇気――母が抱える葛藤の深さに、私はまだ気づけていなかった。

初めての「介助」
母が初めて私に助けを求めたのは、それから数週間後のことだった。ある日、母がトイレのドアを少しだけ開けたまま、私を呼んだ。
「ちょっと手を貸してくれる?」
その言葉に驚きながらも、私はすぐに駆け寄った。母は便座に座ろうとする途中でバランスを崩しそうになっていた。私は母の腕を支えながら、ゆっくりと便座に腰掛けさせた。
「ごめんね、ありがとう。」
母が小さな声でそう言った瞬間、私の胸が締め付けられるようだった。母にとって、この一言がどれほど重かったのか。その「ごめんね」には、自分の衰えを認めたくない気持ちと、私に負担をかけたくないという思いが込められているように感じた。
私はただ笑って、「大丈夫だよ」と言うしかなかった。それでも、母の手に触れた感覚が、私の中に小さな決意を芽生えさせた。「これから母の支えになろう」と。
母のプライド
母はそれ以来、少しずつ私に助けを求めることが増えた。しかし、それは決して当たり前のようにではなく、何かを諦めるような表情とともにだった。
「自分のことくらい自分でできるようになりたいのに。」
母がそう呟いたとき、私は初めて、母が抱えるプライドに気づいた。母にとって「排泄の介助を受ける」という行為は、単なる日常の一部ではなかった。それは、自分の尊厳が揺らぐ瞬間でもあったのだ。
私は母に寄り添いながら、少しでもその尊厳を守れる方法を考えた。「トイレの手すりをつけよう」「母の動線を短くしよう」――そうした小さな工夫を重ねる中で、私は介護が単なる「助ける行為」ではなく、「相手の気持ちを守る行為」であることを学び始めていた。
新たな日常の始まり
母のトイレ問題は、家族全体の生活に少しずつ影響を及ぼしていった。外出する際はトイレの場所を確認し、家ではタイミングを見計らって声をかけるようになった。
「2時間に一度くらい行っておこうか。」
私は母にそう声をかけるたびに、母の表情を窺った。母が無理をしていないか、嫌がっていないか。家族の中で一番母と向き合う時間が長くなった私は、自然と母の気持ちに敏感になっていた。
そしてその日常の中で、私は一つの確信を持つようになった。「排泄の介助」とは単なる世話ではない。それは、相手が安心して生きていくための大切な手段だということ。そしてその中で、相手のプライドや尊厳を守ることが最も重要なのだと。
終わりのない旅の始まり
母との新しい日常は、まだ始まったばかりだった。この先どんな困難が待ち受けているのか分からない。それでも、私は母の「ありがとう」という言葉を支えに、進んでいこうと思った。
介護は終わりのない旅かもしれない。それでも、その旅の中で母と過ごす一瞬一瞬は、何にも代えがたい時間になるだろう。私はそう信じていた。