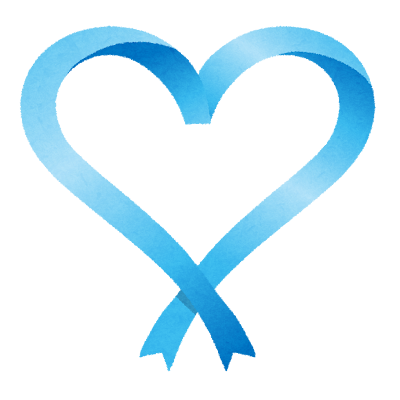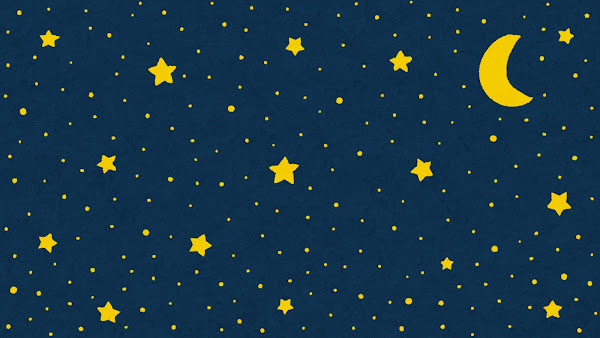
【第二章:見えない壁と不安の中で】
母の介護を始めて半年が経った頃、私の心と体には限界が近づいていることを感じていた。毎日繰り返されるルーティン。朝起きて母を起こし、食事の介助をし、リハビリを手伝い、昼食の準備をする。午後は母を外に連れ出すこともあるけれど、それも私の気力が続く時だけだ。
経済的な負担
介護生活が始まって一番の不安は、お金のことだった。東京での仕事を辞めた私は、貯金を切り崩しながら生活をしている。地方は生活費が安いと思っていたけれど、介護には想像以上にお金がかかる。
車の維持費、医療費、介護用品……細かい出費が積み重なり、どれも削るわけにはいかない。「介護保険があるから大丈夫」と周りは言うけれど、現実には保険でカバーできる範囲は限られている。
「この先、どうなるんだろう。」
そう考えると、胸が苦しくなる。
周囲の目とプレッシャー
村の中で私は「介護している娘さん」として見られている。親戚や近所の人たちは「大変だね」「偉いね」と声をかけてくれるけれど、その優しさが時には重荷になる。
「真由美ちゃんは本当に立派だね。私たちには真似できないわ。」
そんな言葉を聞くたびに、「立派じゃなくてもいいから自由が欲しい」と思う自分がいるのに気づく。
でも、それを誰にも言えない。母を見捨てるわけにはいかないし、田舎では何をするにも人の目が気になる。この村では、私の苦しさを共有できる人はいないように思えた。
孤立感との闘い
都会で働いていた頃、私は友達や同僚と愚痴をこぼし合い、笑い飛ばすことで日々のストレスを乗り越えていた。けれど、この村ではその相手がいない。携帯で友人たちと連絡を取ることもあるけれど、「元気にしてる?」という一言にすら、返事をする気力が湧かない。
「田舎でゆっくりしてるんでしょ?」
そんな言葉を聞くと、私はただ「うん」とだけ答える。実際の生活を話しても、きっと理解してもらえない。私の孤独は、都会から離れたことでさらに深まっていく気がした。
母との衝突
母との生活は、穏やかではいられない時も多かった。ある日のことだ。私は朝から疲れ切っていて、母の着替えを手伝っている最中に、イライラが爆発してしまった。
「お母さん、もう少し自分でできないの?」
その言葉を口にした瞬間、母の表情が曇った。
「ごめんね……迷惑かけて。」
母のその一言で、私は罪悪感に押しつぶされそうになった。どうしてあんなことを言ってしまったのか。自分でもわからない。ただ、心の余裕がなかった。
その夜、私は母が眠った後、一人で泣いた。
小さな希望
そんな生活の中で、ある日、ケアマネージャーの佐藤さんが訪問してくれた。彼女は私より少し年上で、柔らかな笑顔が印象的な女性だった。
「真由美さん、一人で抱え込みすぎないでくださいね。地域のサービスも使いながら、少しでも楽になりましょう。」
そう言って、訪問介護やデイサービスについて詳しく説明してくれた。
「でも、母が嫌がるんじゃないかって……。」
私が不安を口にすると、佐藤さんは優しく頷いた。
「最初はそう思うかもしれません。でも、お母様も真由美さんの負担が減るなら安心されると思いますよ。」
その言葉に、私は少しだけ救われた気がした。私一人で全てを背負う必要はないのだと、ほんの少しだけ思えるようになった。