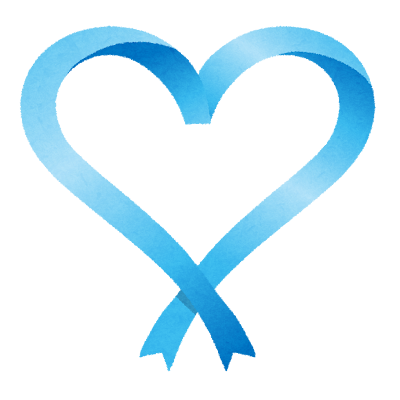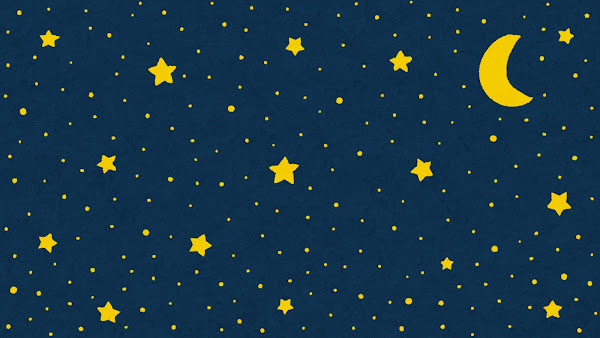
【第一章:地方の静けさと介護の始まり】
春の柔らかな日差しが窓から差し込んでくる。私は古びた実家の居間に座り、ぼんやりと庭を眺めていた。庭に咲く梅の花が、少しだけ私の気持ちを和らげてくれる。でも、それもほんの一瞬だ。
2年前、東京で働いていた私は、母が脳卒中で倒れたという一報を受けて、この田舎町に戻ってきた。それまでの私は、地方で暮らすことなんて考えたこともなかった。田舎に戻れば、昔ながらの穏やかな生活が待っているなんて甘い幻想を抱いていたわけじゃないけど、ここまで現実が厳しいとは思っていなかった。
地方での介護の始まり
「真由美、東京での生活を捨ててまで戻るなんて、大変だったでしょう?」
近所のおばさんがそう言うたびに、私は笑顔で「そんなことないですよ」と答える。でも、心の中では「大変じゃないわけないでしょう」と叫びたくなる。母を見捨てる選択肢なんて最初からなかった。だけど、ここでの生活は、想像以上に私を追い詰めていた。
まず、移動が不便だ。車がなければどこにも行けない。母の通院のために、私はペーパードライバーを卒業し、車を買った。東京では電車と徒歩で事足りていたのに、ここでは車がないと生活そのものが成り立たない。
孤独との戦い
さらに、孤独がじわじわと心にしみ込んでくる。都会の賑やかさは遠い記憶のようだ。仕事を辞めて戻ってきた私は、介護と家事で一日が埋め尽くされている。気軽に話せる友人は、ほとんどいない。村の人たちは親切だけど、どこか距離感がある。世代の違いもあって、話題が噛み合わないことが多い。
「大変ねぇ。でも、親孝行だわ。」
そう言われるたびに、私は複雑な気持ちになる。もちろん、母の世話をすることに後悔はない。それでも、自分の人生を見失っているような感覚に囚われることがある。
母との向き合い方
母は、発症後に右半身が不自由になり、言葉も不自由になった。でも、認知機能はしっかりしていて、私の顔を見ると申し訳なさそうにする。
「ごめんね、真由美。こんな体になっちゃって。」
母がそう言うたびに、胸が締めつけられる。
「お母さん、謝らないでよ。一緒に頑張ろうって言ったじゃない。」
そう言いながらも、心のどこかで「いつまで続くんだろう」と思ってしまう自分が嫌だった。
限界が見え始める
地方の静かな生活は、一見すると穏やかで平和に見える。でも、介護をする私にとっては、それが逆に重荷になることもあった。日常の変化が少なく、逃げ場もない生活に、少しずつ疲弊していく。
夜、母が眠った後、私は窓の外を眺めるのが習慣になった。暗闇の中で星がきらめいている。それを見ていると、少しだけ気持ちが軽くなる気がするけど、それも束の間だ。明日が来れば、また同じ日々が始まる。
「これでいいのかな……私の人生、これでいいのかな……。」
そんな思いが、いつの間にか私の心に居座っていた。